複合材料で差別化するFJコンポジット(北海道・千歳市)。転造タップの下穴加工がユキワ精工製スーパーG1チャックで下穴加工径0.01が1発て。
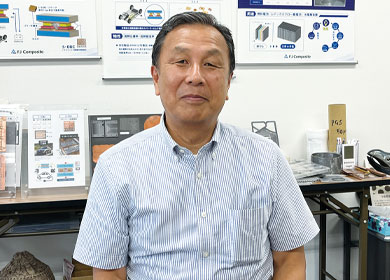
創業者の津島社長
FJコンポジットは2002年に起業し、社名が示す通り、複合材料の開発、製品化を通じて、社会貢献を果たしてきた。
創業者の津島社長は「前職で炭素繊維に関わる事業に携わり、扱っていた複合材が評価され、40歳の時に静岡・富士市で独立。燃料電池用セパレータなどの開発を手がけ、2015年には、出身の北海道に新工場を建設、移転して、今日に至っている」と語る。
複合材料開発のベースにあるのは、異種金属の接合にあり、溶かして着けるロウ付けなどとは違う「拡散接合」と呼ばれる方法にあると言う。
「たとえば、セラミックと銅の接合によるS‐DBC。パワー半導体に最適な回路基板で、EV車のパワーコントロールユニットや大電流のモータなどに採用されている」。
取引企業は30社~40社。売上高では海外が9割、うち8割が韓国で占める。
「取引企業には、量産前の試作・開発に従事する企業も多く、一例を挙げれば、不慮の災害などに備える大型蓄電池の要を成すレドックスフロー電池、その主要部品となる双極板が今年の年末から量産体制に入っていく」。
製品化に当たっては、FJコンポジットでも、試作開発、そのための金型づくりを手がけており、ワイヤ放電加工機をはじめ、フライス関連では、ブラザーのスピーディオやファナックのロボドリルなどが活用されている。
フライス関連で、直接、現場で関わっている技術開発の櫻井さんに「カーボン材料の試験片の加工や特性の確認、新規材料の試験、アルミ型の量産試作などを行っている」との役割を紹介してもらいながら「半年前からセラミックと接合された銅の転造タップ(M3)の仕事が入ってきたが、下穴の径の加工がブレてしまって安定せず、話にならない」事態に直面、ユキワ精工製スーパーG1チャック採用の背景に言及してもらった。ユキワ精工を知ったのは、今年に入り、取引商社から紹介されたのがきっかけで、この下穴加工で苦慮する少し前のことだったと言う。
「ユキワ精工の営業と技術それぞれの担当の方が来社され、スーパーG1チャックについて、詳細をお聞きする機会を得た」「ブラザー工業の技術担当者からの推薦もあった」ことから、従来のツーリングに代えて、困っていたタップの下穴加工でテストを実施することに。
「すぐに課題が解決された。狙っていた下穴加工の径、0・01が簡単に、一発であけられるようになった。顧客が今の量産試作から量産に入れば、年間で14万穴の仕事を請けられるようになる、言わば、その体制が整ったことになる」と櫻井さんは胸をなでおろしている。
現状ではスーパーG1チャック4本だが、顧客が量産に入れば、年間14万穴におよぶタップ加工の仕事が待っている。
津島社長は「スーパーG1チャックの追加オーダーはもちろん、マシニングセンタの増強も視野に入れている」と語り、櫻井さんは「量産がスタートすれば、スーパーG1チャックによって、工具寿命がどれだけ伸びていくか、是非とも、検証していきたい」との意欲を語った。

試作、開発を手がける櫻井さん。スーパーG1チャックを採用することでタップの下穴加工で狙っていた径が一発で出たと言う

